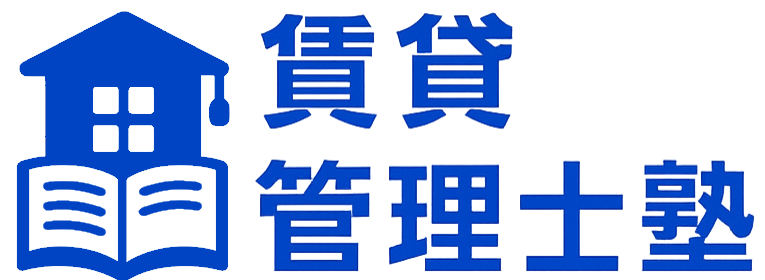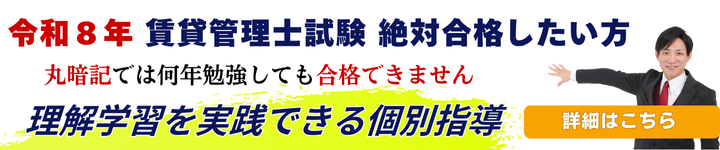- 敷金が20万円の場合、賃料減額請求権の行使により敷金も14万円に減額になるので、賃貸人は敷金の差額分の6万円を返還しなければならない。
- 賃借人の賃料減額請求権の行使後、物件に雨漏りが発生した場合でも、そのことによる物件の価値の減少は、当該賃料減額請求の判断に際しては、考慮の対象とはならない。
- 賃借人が賃貸人に対し口頭で賃料を7万円に減額するよう通知した場合でも、賃料減額請求権を行使したものと認められる。
- 賃料減額請求権の行使後、毎月8万円の賃料が支払われていた場合において、9万円を正当な賃料額とする裁判が確定したときは、賃貸人は、毎月の賃料の不足分1万円につき、法定利率による利息を付した額の支払を賃借人に請求することができる。
敷金は一般的に「賃料の○ヵ月分」として設定されることが多いですが、賃料減額請求権の行使によって賃料が減額されたとしても、敷金自体が自動的に減額されるわけではありません。
なぜなら、 敷金は賃貸借契約とは別個の契約関係にあるからです。敷金はあくまで契約締結時に取り決められた金額であり、賃料が減額されたことにより敷金も減額されると考えるのは誤りです。したがって、貸主が「敷金の減額分」を返還する義務はありません。
このように理由が分かるとと頭に定着しやすいです。個別指導では、理解をしながら学習できます!理解ができない方、周辺知識が頭に入っていない方は、個別指導で次の試験の合格を私と一緒に目指しましょう!
賃料増額・減額請求権は、賃貸借契約の締結後に、経済的要因や物件の状態の変化により、賃料が不相当となった場合に認められる権利です。
この賃料増減額請求がなされた後に、新たに賃料の増減に影響を与える事情(例えば雨漏りなどの物件価値の低下)が発生したとしても、その影響を考慮するには、新たに増減額請求をしなければなりません。つまり、すでに行われた減額請求の判断においては、請求後に生じた事情は考慮の対象とならないのが原則です。
この考え方は、最判昭和44年4月15日の判例でも示されており、賃料増減額請求後に発生した事情は、その請求の判断に影響を及ぼさないとされています。
よって、賃料減額請求がなされた後に発生した雨漏りによる物件価値の低下は、その請求の判断においては考慮されないので正しいです。
上記は分かりづらいので、具体例を入れた分かりやすい解説は個別指導で行います!
賃料減額請求権の行使方法について、 法律上特別な形式は定められていません。そのため、書面による請求に限らず、口頭や電子メールなどの電磁的記録を用いても有効とされます(借地借家法32条1項)。
したがって、本問のように賃借人が賃貸人に対して口頭で賃料の減額を申し入れた場合であっても、賃料減額請求権の行使として認められます。
賃借人が賃料減額請求を行った場合であっても、賃貸人は自身が正当と考える賃料額を請求することが可能です。その後、裁判において適正な賃料額が確定すると、過去の支払い額と確定賃料との差額の取り扱いが問題となります。
借地借家法32条3項では、 確定賃料が賃貸人の受領額を超える場合、賃借人はその不足額を支払う義務があるとされており、これに関する利息については 法定利率(年1割)が適用されます。逆に、受領額が確定賃料を超えていた場合は、賃貸人が超過分を賃借人に返還しなければならず、その場合の利息は年1割となります。
本問では、賃料減額請求後に賃借人が毎月8万円を支払い続け、裁判で正当な賃料が9万円と確定しました。したがって、賃貸人は不足分の1万円に対し、法定利率に基づく利息を付した額を賃借人に請求することができます。
この点は重要なので個別指導で詳しく解説します。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険