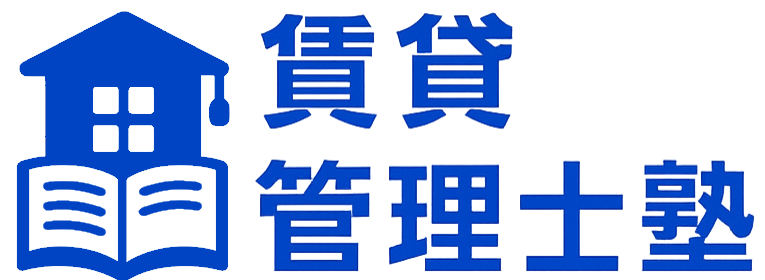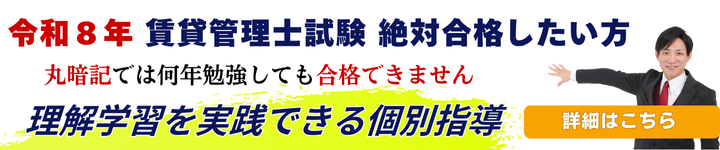- 賃借人が賃料を滞納した場合、賃貸借契約書が執行認諾文言付きの公正証書により作成されているときは、賃貸人は、改めて訴訟を提起して確定判決を得ることなく、滞納賃料の請求について強制執行をすることができる。
- 期間内に滞納賃料の支払がない場合には期間の経過をもって賃貸借契約を解除する旨の通知は、内容証明郵便により行わなければ、賃借人が滞納賃料を支払わないまま所定の期間が経過しても、契約解除の効力は生じない。
- 滞納賃料の支払督促に対しては異議の申立てがなくても、当該支払督促について賃貸人が行った仮執行宣言の申立てに際し、賃借人が2週間以内に異議の申立てをすれば、通常の民事訴訟の手続に移行する。
- 既にA簡易裁判所において同一年内に10回の少額訴訟を提起している賃貸人が、同一年内に初めてB簡易裁判所に対し、その管轄に属する滞納賃料の支払請求訴訟を提起する場合には、少額訴訟を選択することができる。
賃貸借契約書が「 執行認諾文言付きの公正証書」として作成されている場合、賃貸人は、改めて訴訟を起こして確定判決を得ることなく、滞納賃料について 強制執行を行うことができます(民事執行法22条5号)。
■執行認諾文言付き公正証書とは?
これは、「債務者(賃借人)が直ちに強制執行に服する(従う)」旨の陳述が記載された公正証書で、「執行証書」とも呼ばれます。この 執行証書には、 裁判の確定判決と同じ効力があるため、賃貸人は裁判を経ずに強制執行を申し立てることができます。
執行証書がある場合、迅速に賃料回収が可能となるため、賃貸借契約を締結する際には、賃貸人側にとって非常に有利な契約形態となります。
「滞納賃料の支払いがない場合に、期間の経過をもって賃貸借契約を解除する旨の通知は、内容証明郵便で行わなければならない」という記述は誤りです。
契約解除の意思表示は、相手方に到達すれば効力を生じる(民法97条1項)ため、必ずしも内容証明郵便で送る必要はありません。
■なぜ内容証明郵便を利用するのか?
内容証明郵便は、通知内容や発送日を証拠として残すために利用されます。
賃借人が「そんな通知は受け取っていない」と主張するリスクを回避するために、実務上は内容証明郵便を利用するのが一般的ですが、法的には必須ではありません。
支払督促は、賃貸人(債権者)が裁判所を通じて、賃借人(債務者)に対し滞納賃料の支払いを求める手続きです。
支払督促が賃借人に送達されてから 2週間以内 に異議を申し立てると、支払督促の効力は失われ、 通常の民事訴訟に移行します。
よって、本肢は正しいです。
この点は「異議がない場合」も併せて勉強すべき内容なので、この点は個別指導で解説します。
支払督促は、賃貸人(債権者)が裁判所を通じて、賃借人(債務者)に対し滞納賃料の支払いを求める手続きです。この手続きでは、以下のような流れで異議の申立てができます。
- 最初の異議申立て(民訴法393条)
支払督促が賃借人に送達されてから 2週間以内 に異議を申し立てると、支払督促の効力は失われ、 通常の民事訴訟に移行します。
異議がない場合、賃貸人は仮執行宣言の申立てを行うことができます。 - 仮執行宣言後の異議申立て(民訴法395条)
賃貸人が仮執行宣言を申し立て、裁判所がこれを認めると、支払督促は確定判決と同じ効力を持つようになります。
ただし、賃借人は仮執行宣言が送達されてから2週間以内に異議を申し立てることができ、その場合、通常の民事訴訟に移行します。
よって、本肢は正しいです。
少額訴訟は、60万円以下の金銭支払請求について、簡易・迅速な解決を目的とした訴訟手続きですが、1人の原告が同一の簡易裁判所で提起できる回数には制限があります。
民事訴訟規則223条
「 1人が同一年内に同一の簡易裁判所において少額訴訟を提起できるのは 10回までである。」
つまり、 同じ簡易裁判所での少額訴訟は年10回までしかできません。
本問では、賃貸人はすでにA簡易裁判所で10回の少額訴訟を提起しているため、A簡易裁判所では11回目の少額訴訟はできません。
しかし、B簡易裁判所に対しては、今年初めての提起となるため、B簡易裁判所の管轄に属する事件であれば、少額訴訟を選択することが可能です。
本肢は関連ポイントも重要なので、個別指導で解説します。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険