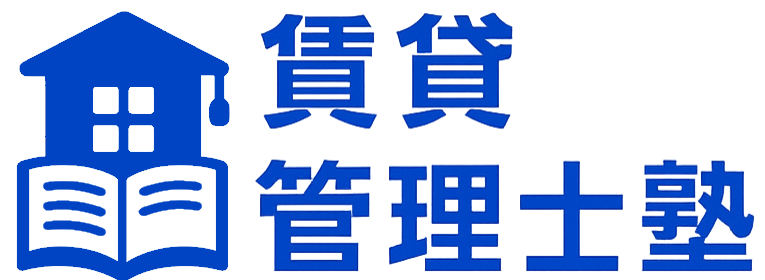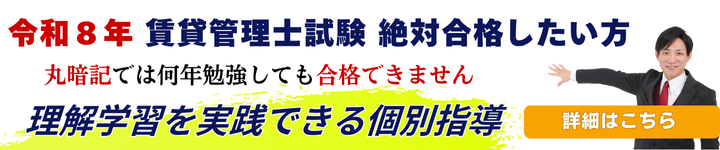ア 賃貸借契約の契約期間は、50年を超えることができない。
イ 賃貸借契約では、契約期間を定めることが賃貸借契約の成立要件である。
ウ 賃貸借契約において、賃貸人が契約の更新を拒絶する旨を通知したが、賃借人が期間満了後も賃貸住宅を使用し続け、賃貸人がこれに異議を述べない場合、賃貸借契約は更新されたものとみなされる。
エ 賃貸借契約において、賃貸人が契約期間満了を原因として契約を終了させる更新拒絶の通知には正当事由の具備が必要となるところ、財産上の給付(いわゆる立退料)は正当事由の補完要素として考慮されるに過ぎない。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ
民法604条では、「 賃貸借契約の期間は50年を超えることができない」と規定されています。しかし、この規定は すべての賃貸借契約に適用されるわけではありません。
借地借家法では、建物の賃貸借については民法604条の適用を受けないとされています。そのため、建物の賃貸借契約においては、 契約期間を50年を超えて設定することも可能です。(ちなみに、借地借家法における建物賃貸借の期間について、 1年未満とする場合、 期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます。)
つまり、
- 民法:賃貸借契約の期間は50年を超えることができない(民法604条)。
- 借地借家法:建物賃貸借には民法604条の規定が適用されないため、50年を超える契約も可能。
このように、賃貸借契約の対象が 建物であるかどうか によって、契約期間の制限が異なります。
賃貸借契約を成立させるためには、 契約期間を定めることは必須ではありません。よって、本肢は誤りです。
賃貸借契約が成立するためには、次の条件が満たされる必要があります(民法601条:賃貸借契約の成立要件)。
- 貸主(賃貸人)が目的物を 使用収益させることを約束すること
- 借主(賃借人)がその対価として 賃料を支払うこと
- 契約終了時に目的物を 返還すること
この3つが合意されれば、賃貸借契約は成立します。
普通建物賃貸借契約では、契約期間が満了すると契約が終了するのが原則です。ただし、賃貸人が期間満了の1年前から6月前までの間に、 賃貸人(貸主)が正当事由をもって更新を拒絶しない限り、契約は 自動的に更新されます(法定更新)。
仮に 賃貸人が正当事由をもって契約更新を拒絶したとしても、「 ①賃借人(借主)が契約期間満了後も引き続き建物を使用していて」かつ「 ②賃貸人(貸主)がそれを知りながら、すぐに異議を述べずに放置していた」場合、契約は 自動的に更新されます(法定更新)。
本肢は、①②を満たすので、賃貸借契約は更新されたものとみなされます(法定更新)。よって、正しいです。
普通建物賃貸借契約において、契約期間が満了したからといって、賃貸人(貸主)が一方的に契約を終了させることはできません。
契約の更新を拒絶するためには、「正当事由」が必要です(借地借家法28条)。
判例では、次の5つの要素を総合的に考慮し、正当事由があるかどうかを判断します(最判昭46.11.25)。
- 貸主・借主が建物を必要とする事情
例:貸主が自分で住む必要がある、借主の転居先がないなど - これまでの賃貸借契約の経緯
例:貸主が長年にわたり契約更新を許可してきたか、借主が長期間住んでいたかなど - 建物の利用状況
例:借主が正しく利用しているか、放置・転貸していないかなど - 建物の現況
例:老朽化しているか、修繕が必要かなど - 立退料の提供の申し出
例:貸主が借主に立退料を支払う意思があるかなど
そして、 立退料は「 正当事由を補完するもの」として考慮されます。つまり、貸主が立退料を支払うと申し出たからといって、それだけで正当事由が認められるわけではなく、立退料は他の要素と合わせて総合的に判断されるものです。よって、本肢は正しいです。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険