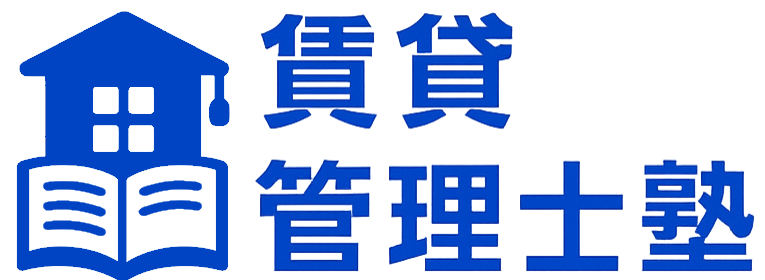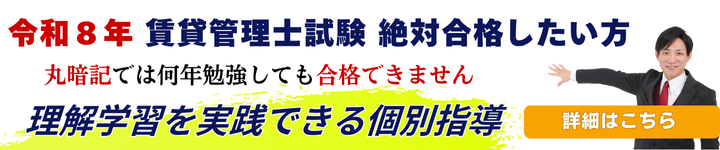ア 保証契約は書面により締結されなければならないため、同契約がその内容を記録した電磁的記録によってなされても無効である。
イ Bが賃料の支払を遅滞した場合、AがCに対して連帯保証債務の履行を請求するためには、AB間の賃貸借契約を解除しなければならない。
ウ AC間の連帯保証契約は、主債務の範囲に含まれる債務の種別を問わず、極度額を定めなければ効力を生じない。
エ CがAに対して主債務の元本及び主債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供することを請求した場合、Aには情報提供義務がある。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
保証契約は、書面で締結しなければ効力を生じません(民法446条2項)。つまり、口頭での保証契約は無効となります。しかし、書面での締結に代えて、契約内容を電磁的記録(電子データなど)によって記録した場合、その契約は「書面によってしたもの」と法律上みなされます(同条3項)。
したがって、「保証契約が電磁的記録によってなされた場合は無効である」とする記述は誤りです。電磁的記録による保証契約も、有効に成立します。
賃貸借契約において、賃借人(B)が賃料の支払いを遅滞した場合、賃貸人(A)はBに対して支払いを求めることができます。それと同時に、Aは連帯保証人(C)に対しても、賃貸借契約を解除することなく連帯保証債務の履行を請求することができます(民法452条1項)。
つまり、連帯保証契約では、主債務者(B)が債務を履行しない場合、債権者(A)は直接、保証人(C)に対して支払いを求めることができるのです。そのため、「AがCに請求するためには、AB間の賃貸借契約を解除しなければならない」という記述は誤りです。
連帯保証契約の中でも、特に「個人根保証契約」に該当する場合は、極度額(保証の上限額)を定めなければ契約の効力が生じません(民法465条の2)。これは、個人の保証人が際限なく責任を負わされることを防ぐための規定です。
問題文では、Cが個人であることが前提とされているため、AC間の連帯保証契約が個人根保証契約に該当します。その場合、保証の対象となる債務の種類に関係なく、極度額を定めることが法律上の要件となります。したがって、この記述は正しいです。
保証人は、債務の履行責任を負う立場にあるため、主たる債務の状況を適切に把握する必要があります。そのため、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証している場合、債権者(A)は保証人(C)から請求があったときに、以下の情報を提供する義務を負います(民法458条の2)。
- 主債務の不履行の有無
- 主債務の元本残額、利息、違約金、損害賠償などの額
- そのうち弁済期が到来しているものの額
これは、保証人が自身の責任を適切に判断できるようにするための重要なルールです。したがって、保証人CがAに対して情報提供を求めた場合、Aにはこれに応じる法的義務があります。この記述は正しいといえます。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険