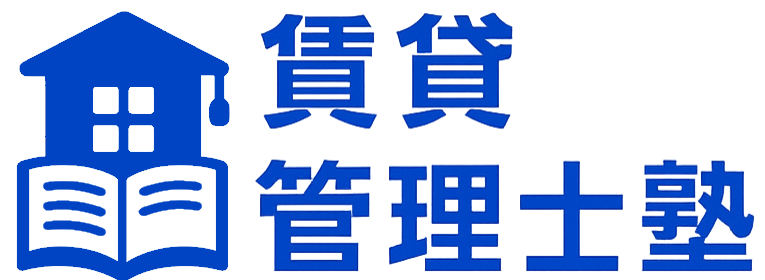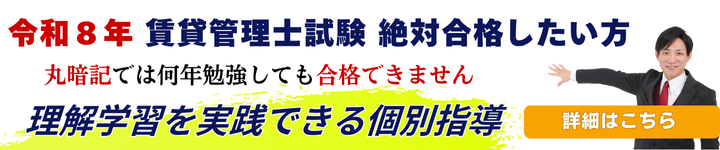- 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約重要事項説明にあたって、説明の相手方の賃貸住宅経営の目的・意向を十分に確認すべきである。
- 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約重要事項説明の相手方が高齢である場合は、過去に賃貸住宅経営の経験が十分にあったとしても、説明の相手方の状況を踏まえた慎重な説明を行うべきである。
- 特定転貸事業者は、ITを活用した方法で特定賃貸借契約重要事項説明を実施する場合、説明の相手方が図面等の書類及び説明を十分に理解できる映像を視認できるか、又は、双方が発する音声を十分に聞き取ることができる環境で実施しなければならない。
- 特定転貸事業者は、ITを活用した方法で特定賃貸借契約重要事項説明を実施する場合、説明の相手方が承諾した場合を除き、重要事項説明書をあらかじめ送付しておく必要がある。
特定転貸事業者(サブリース業者)は、特定賃貸借契約の重要事項説明を行う際に、説明の相手方である賃貸住宅オーナーの賃貸住宅経営の目的・意向を十分に確認する必要があります。これは、説明の相手方の状況に応じた適切な説明を行うためです。
【重要事項説明の目的】
特定賃貸借契約の重要事項説明は、サブリース契約の仕組みやリスクを十分に理解してもらうことを目的としています。そのため、説明の相手方の知識・経験・財産状況・リスク管理能力などを考慮した上で説明を行うことが望ましいとされています。
【サブリースガイドライン(第30条関係(4))による留意点】
サブリースガイドラインでは、以下の3点について特に留意すべきとされています。
- 賃貸住宅経営の目的・意向を十分に確認すること
→賃貸住宅オーナーがサブリース契約を通じて何を目的としているのか(安定収益の確保、資産活用など)を把握する。
→その目的に照らして適切な説明を行う。 - 賃貸住宅経営の目的等に照らして、マスターリース契約のリスクを十分に説明すること
→空室リスク、賃料減額リスク、契約解除の可能性などについて明確に伝える。 - 説明の相手方が高齢の場合は、状況を踏まえ慎重に説明すること
→高齢のオーナーには、より丁寧で分かりやすい説明を行う。
→必要に応じて家族などの同席を求める。
つまり、ガイドラインに基づき、特定賃貸借契約の重要事項説明を行う際には、単に契約の概要を伝えるだけでなく、説明の相手方の属性や状況を踏まえた適切な説明が求められます。そのため、賃貸住宅経営の目的・意向を十分に確認することは適切な対応であると言えます。
特定転貸事業者(サブリース業者)は、特定賃貸借契約の重要事項説明を行う際、説明の相手方が高齢である場合には特に慎重な対応が求められます。たとえ相手方が過去に十分な賃貸住宅経営の経験を持っていたとしても、高齢になることで身体的な衰えが生じるほか、判断能力が短期間で変化する可能性もあるためです。
サブリースガイドライン(第30条関係(4))においても、高齢のオーナーに対する説明は、その状況を十分に考慮し、慎重に行うべきであるとされています。このような配慮は、高齢のオーナーが契約内容を適切に理解し、リスクを十分に認識したうえで判断できるようにするために必要不可欠です。
そのため、特定転貸事業者は単に契約の内容を説明するだけでなく、相手方の理解度を適宜確認しながら、わかりやすく丁寧に説明を行うことが求められます。また、必要に応じて家族や信頼できる第三者の同席を促すなど、高齢者が不利益を被ることのないよう慎重な対応を心がけることが望ましいです。
特定転貸事業者がITを活用して特定賃貸借契約の重要事項説明を実施する場合、適切な環境を整えることが求められます。具体的には、説明者および説明を受ける者の双方が、図面などの書類や説明の内容を十分に視認できる映像環境を確保し、「かつ」、相互の音声が明瞭に聞き取れる状態であることが必要です。また、説明の過程において、双方が双方向でやりとりできる環境であることも重要とされています。
これは、「解釈・運用の考え方」においても明確に示されており、ITを活用した重要事項説明では、映像と音声の両方が適切に機能することが必須条件とされています。本肢では「又は」という表現が使用されており、映像の視認または音声の聞き取りのいずれか一方の条件が満たされていればよいとも解釈できる内容となっています。しかし、実際には、映像と音声の両方が確実に機能し、円滑な双方向のやりとりが可能であることが求められるため、本肢の記述は「又は」となっているので不適切です。
特定転貸事業者がITを活用して特定賃貸借契約の重要事項説明を行う場合、原則として、重要事項説明書および添付書類を事前に送付しておく必要があります。これは、説明を受ける者が事前に内容を確認し、十分に理解したうえで説明を受けることができるようにするための措置です。
「解釈・運用の考え方」においても、ITを活用した重要事項説明においては、説明の相手方が承諾した場合を除き、事前に重要事項説明書および添付書類を送付することが求められています。通常は、これらの書類の送付から一定期間を置いた後に重要事項説明を実施することとされていますが、説明の相手方が事前送付を不要とすることに同意した場合は、重要事項説明書等の事前送付は不要です。
したがって、相手方の承諾がない限り、重要事項説明書を事前に送付しなければならないという本肢の記述は適切であると言えます。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険