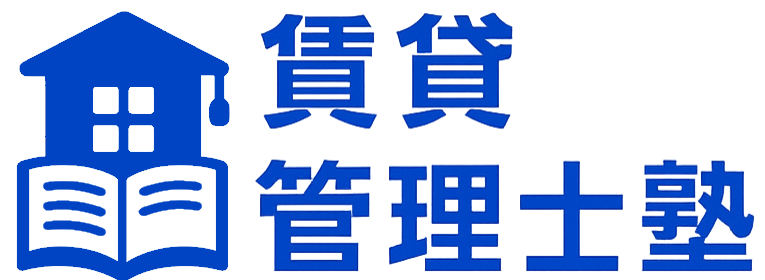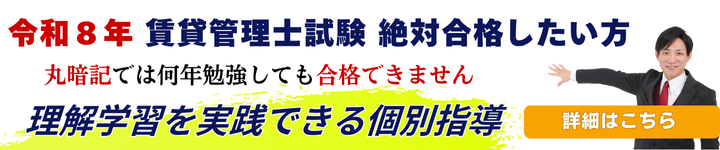- 父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けて子が一定の耐震性、省エネルギー性などを備えた良質な賃貸住宅を建てた場合、1,000万円まで贈与税が非課税となる。
- 初めて賃貸住宅経営を開始した人が3年以内に死亡した場合は、その賃貸住宅の敷地を貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することはできない。
- 法定相続人が2人(うち1人は相続放棄をした。)の場合の相続税の遺産に係る基礎控除額は、4,200万円(=3,000万円+600万円×2人)である。
- 令和7年年2月1日に祖父から贈与により取得した財産について暦年課税を適用し、同年3月1日に父から贈与により取得した財産については相続時精算課税を選択した場合、贈与税の基礎控除は合計220万円まで認められる。
父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた資金を利用して住宅を取得する場合、一定の要件を満たせば贈与税が非課税となる制度があります。しかし、この非課税措置は「自己の居住の用に供する住宅」に限られるため、賃貸住宅の取得には適用されません。
具体的には、以下のように非課税限度額が異なります。
- 一定の耐震性、省エネルギー性、バリアフリー性を備えた住宅
→ 最大1,000万円まで非課税 - それ以外の住宅
→ 最大500万円まで非課税
つまり、贈与を受けた資金を使って良質な賃貸住宅を建てた場合でも、「自己の居住の用に供する住宅」ではないため、贈与税の非課税措置を受けることはできません。
小規模宅地等の特例では、相続財産のうち一定の用途に供されていた土地の評価額を減額できる制度があります。その中で、「貸付事業用宅地等」としての適用を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。
<貸付事業用宅地等の適用要件>
- 被相続人が生前に貸付事業を行っていたこと
- 被相続人が相続開始前3年超の期間にわたり貸付事業を継続していたこと
このため、被相続人(死亡した者)が初めて賃貸住宅経営を開始してから3年以内に死亡した場合、その賃貸住宅の敷地は「貸付事業用宅地等」に該当せず、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。
相続税の課税対象となる遺産総額からは、基礎控除額を差し引くことができます。基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
<基礎控除額の計算式>
3,000万円+600万円×法定相続人の数
<相続放棄した場合の扱い>
相続放棄をした人は遺産分割には関与できませんが、基礎控除額の計算上は法定相続人の数に含めることになっています。
<本件の場合>
法定相続人の数:2人(うち1人が相続放棄)
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
したがって、相続放棄をした人がいても、基礎控除額は4,200万円となり、適用される計算は正しいことになります。
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方式があります。これらの制度の選択により、基礎控除の適用額が変わります。
<2023年度税制改正による変更点>
2023年度の税制改正により、相続時精算課税制度にも基礎控除(年110万円)が創設されました。これにより、相続時精算課税を選択した場合でも110万円までの贈与は贈与税がかからない仕組みとなりました。
<本件の場合>
- 令和7年2月1日に祖父から贈与(暦年課税を適用)
→暦年課税の基礎控除110万円を適用可能 - 令和7年3月1日に父から贈与(相続時精算課税を適用)
→相続時精算課税の基礎控除110万円を適用可能
基礎控除の合計
=暦年課税の基礎控除110万円+相続時精算課税の基礎控除110万円=合計220万円
したがって、本件のケースでは、贈与税の基礎控除の合計は220万円まで認められるため、本肢の記述は正しいとなります。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険