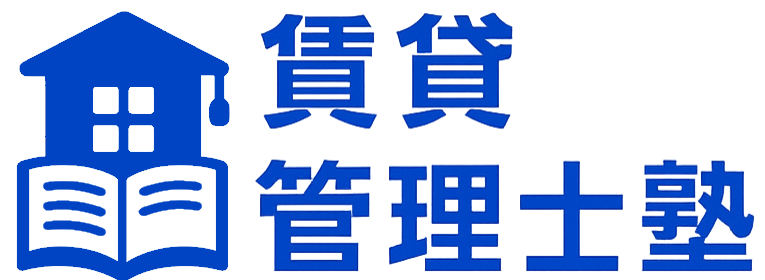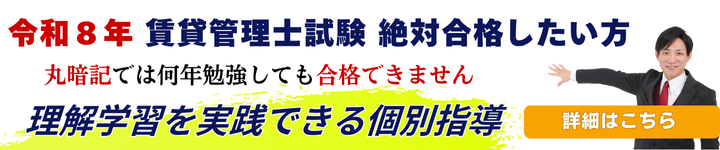- 木造在来工法は、建物重量が軽く、設計の自由度が高く、施工しやすいが、鉄骨鉄筋コンクリート造と比べて防火・耐火性能に劣る。
- 木造ツーバイフォー工法(枠組壁工法)は、構造安全耐力及び居住性能において優れているが、気密性が高いため、建物内部に湿気がたまりやすい。
- 鉄骨造は、比較的軽量であるため高層建物に採用されることが多いが、耐火被覆が必要である。
- CFT造は、現場での鉄筋工事や型枠工事が不要となり、省力化工法となっているが、強度が低く、柱間隔や階高を大きく確保することが難しい。
木造在来工法(軸組工法)は、日本で広く採用されている伝統的な建築工法であり、以下のような特徴があります。
- 建物の重量が軽いため、地盤への負担が少なく、耐震性を確保しやすい。
- 設計の自由度が高いため、間取りの変更や増改築が比較的容易。
- 施工がしやすいため、工期が比較的短く、コストを抑えやすい。
一方で、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)や鉄筋コンクリート造(RC造)と比較すると、以下の点で劣る部分があります。
- 防火・耐火性能が低いため、火災時の延焼リスクが高い。
- 耐久性が低いため、定期的なメンテナンスが重要。
そのため、賃貸住宅の構造として、木造在来工法はアパートに多く採用され、SRC造やRC造はマンションの建築に適しているとされています。
木造ツーバイフォー工法(枠組壁工法)は、耐力壁と剛床を一体化した箱型構造を採用しており、以下のような特徴を持ちます。
✅ メリット(優れた性能)
- 耐震性が高い:面全体で外力を受け止めるモノコック構造のため、地震時の揺れを分散しやすい。
- 耐火性が高い:石膏ボードなどの防火材料を使用し、火の回りが遅くなるため、在来工法よりも耐火性に優れる。
- 断熱性・気密性が高い:壁や床を面で構成するため、隙間が少なく、外気の影響を受けにくい。
- 防音性に優れる:面構造が遮音性を高め、音の伝わりを抑えやすい。
❌ デメリット
- 気密性が高すぎるため、湿気がこもりやすい:通気性が低いため、適切な換気計画が必要。特に、結露やカビの発生を防ぐためには、計画換気システムや調湿機能を備えた建材の採用が求められる。
このような特性から、ツーバイフォー工法は住宅だけでなく、賃貸アパートや商業施設などにも採用されています。ただし、湿気対策を怠ると建物の寿命が縮む可能性があるため、適切な換気計画が重要となります。
鉄骨造(S造)は、鉄骨(鋼材)を主要な構造部材として使用する建築工法であり、以下のような特徴があります。
✅ 鉄骨造のメリット
- 比較的軽量:RC造やSRC造と比べて建物重量が軽く、地盤への負担を軽減できる。
- 高層建築に適している:強度が高いため、柱や梁を細くでき、大空間の確保が可能。オフィスビルや商業施設などでよく採用される。
- 施工期間が短い:工場で鉄骨部材をあらかじめ製造し、現場で組み立てるため、工期を短縮しやすい。
❌ 鉄骨造のデメリット
- 耐火性能が低い:鉄は300℃~500℃程度で強度が低下し、600℃を超えると変形や崩壊のリスクが高まる。そのため、火災時の安全性を確保するために、耐火被覆(耐火材)を施すことが義務付けられている。
- 防音・断熱性能が低い:鉄は熱を伝えやすく、遮音性も低いため、適切な断熱材や防音材を併用する必要がある。
🏢 鉄骨造が採用される建物の例
- 高層ビル・オフィスビル(軽量で柱や梁を細くできるため)
- 商業施設・倉庫(大空間を確保しやすいため)
- マンション(中高層)(RC造より軽く、コストを抑えやすいため)
鉄骨造は高層建築や大規模建築に適していますが、耐火性が低いため、耐火被覆(耐火塗料、吹付けロックウールなど)の施工が不可欠となります。
CFT造(コンクリート充填鋼管構造)は、鋼管の内部にコンクリートを充填することで、鋼材とコンクリートの相乗効果を活かした構造形式です。近年、高層建築や大規模建築において注目されている工法の一つです。
✅ CFT造のメリット
- 強度が高い:
鋼管が外側からコンクリートを拘束することで、コンクリートの圧縮強度が向上。
鋼材がコンクリートを補強し、曲げや引張りにも強くなる。RC造やS造よりも高強度で、柱間隔を広く、階高を高く確保しやすい。 - 剛性(変形しにくさ)が高い:
変形しにくく、大規模建築や高層建築に適している。 - 施工の省力化が可能:
現場での鉄筋工事や型枠工事が不要のため、施工の手間やコストを削減できる。
工期の短縮につながる。 - 耐火性・耐震性が向上:
鋼管が火災時のコンクリートの剥落を防ぎ、耐火性能が向上する。
地震時に粘り強く変形するため、倒壊リスクが低減する。
❌ CFT造のデメリット
- 施工時に高度な技術が必要:
コンクリートを均一に充填する技術が求められる。 - 材料費が比較的高い:
鋼管とコンクリートの両方を使用するため、コストが高くなる場合がある。
🏢 CFT造が採用される建物の例
- 高層ビル・オフィスビル
- 橋梁の柱や耐震補強
- 大規模商業施設
本肢は「CFT造は強度が低く、柱間隔や階高を大きく確保することが難しい」とありますが、実際にはCFT造は強度が高いため、柱間隔や階高を大きく取ることが可能です。したがって、この記述は不適切です。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険