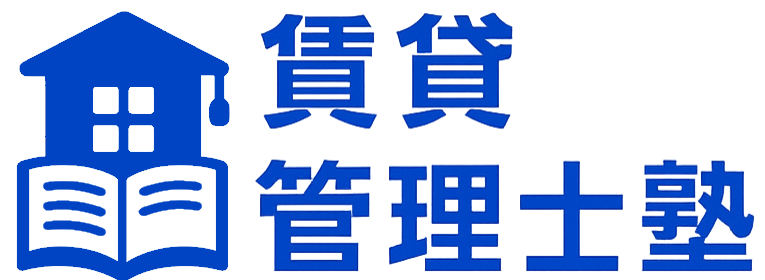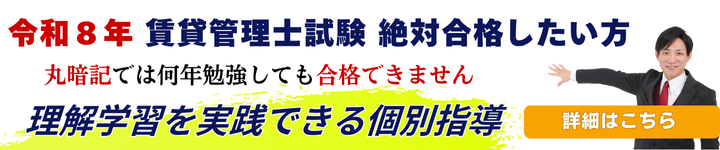- 賃貸不動産経営管理士は、サブリース方式による賃貸借契約に関して、賃貸住宅管理業法が、特定賃貸借契約に係る規律と転貸借契約に係る規律を定めているので、民法や借地借家法などの規律は適用されないことに留意する必要がある。
- 賃貸住宅管理業法では管理業務を、賃貸住宅の維持保全を行う業務とその業務と併せて行う家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務に限定していることから、賃貸不動産経営管理士が原状回復の範囲の決定に係る事務や明渡しの事務に関わることは求められていない。
- 賃貸不動産経営管理士には、賃貸不動産経営を支援する業務として予算計画書、収支報告書、物件状況報告書、改善提案書の作成を担うことが期待されるが、予算差異分析は会計等の専門知識が必要なことから、その分析書は税理士が作成することが義務付けられている。
- 10~30年程度の将来について、いつ頃、何を、どのように、いくらくらいかけて修繕するかを示す長期修繕計画書を作成することは、賃貸住宅の資産価値を維持する上で重要な事務であり、賃貸不動産経営管理士が作成した場合は、専門家としての責任の所在を明確にするために、記名することが望ましい。
賃貸住宅管理業法では、特定賃貸借契約(物件所有者とサブリース業者との契約)に関する規律を定めているものの、転貸借契約(サブリース業者と入居者の契約)に関する直接的な規律は設けられていません。
したがって、 転貸借契約においては、 民法や借地借家法の規定が適用されることになります。
本肢では、「賃貸住宅管理業法が特定賃貸借契約と転貸借契約の両方を規律しているため、民法や借地借家法の規律は適用されない」とありますが、これは誤りです。
賃貸住宅管理業法では、「管理業務」を以下の2つに限定しています。
- 賃貸住宅の維持保全を行う業務
- 家賃・敷金・共益費などの金銭管理業務(維持保全業務と併せて行う場合)
この定義だけを見ると、管理業者が原状回復の範囲決定や明渡しに関わる義務がないように思えますが、実際の賃貸管理業務はこれにとどまりません。
賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅管理業法に定められた管理業務の範囲を超えて、下記のような役割も求められます。
- 原状回復の範囲決定(修繕費用の負担区分の判断など)
- 明渡し業務(退去立会いや賃借人との調整など)
つまり、 賃貸不動産経営管理士は、単に賃貸住宅管理業法に基づく業務だけでなく、実際の管理現場において幅広い役割を担う必要があります。
本肢は「賃貸不動産経営管理士は賃貸住宅管理業法が定める管理業務(維持保全・金銭管理)に限定され、原状回復の範囲決定や明渡し業務に関与する必要がない」と述べていますが、これは誤りです。
賃貸不動産経営管理士は、賃貸不動産の経営を支援する業務として、以下のような書類を作成することが期待されています。
- 予算計画書(賃貸経営の収支計画)
- 収支報告書(実際の収支をまとめた報告書)
- 物件状況報告書(建物の修繕状況や管理状態を記載)
- 改善提案書(賃貸経営の効率化や改善策の提案)
また、これらの書類を作成する過程で、 予算と実績の差異(予算差異分析)を行うことも重要な役割です。
【税理士の独占業務】
税理士法により、税理士の独占業務は以下の3つに限定されています。
- 税務代理(税務署への申告や税務調査の立ち会いなど)
- 税務書類の作成(確定申告書・決算書・法人税申告書などの作成)
- 税務相談(税金計算や節税対策のアドバイス)
予算差異分析は税務に直接関係するものではなく、経営判断のための会計的な分析であるため、税理士の独占業務には該当しません。
そのため、 賃貸不動産経営管理士が予算差異分析を行うことは問題なく、税理士でなければできないという規定もありません。
本肢では、「予算差異分析は税理士が作成することが義務付けられている」とされていますが、これは誤りです。
賃貸住宅の資産価値を維持し、長期的な安定経営を図るためには、計画的な修繕が欠かせません。そのため、 10~30年程度の将来を見据え、「いつ」「何を」「どのように」「いくらかけて」修繕するのかを示す長期修繕計画書の作成が重要になります。
長期修繕計画書には以下のような内容が含まれます。
- 計画期間(10~30年程度)
- 修繕対象(外壁・屋根・給排水設備など)
- 修繕の実施時期
- 概算費用
- 資金計画(修繕積立金など)
【賃貸不動産経営管理士の役割】
家主(オーナー)がこうした計画を立てるのは専門知識が必要であり、管理業者や専門家に依頼するケースが多いです。
賃貸不動産経営管理士は、修繕計画の策定に関する知識を持ち、オーナーに対して適切なアドバイスを行い、計画書を作成する役割を担うことが期待されます。
【責任の明確化】
長期修繕計画書の作成は、専門的な判断を要する業務であるため、 作成者としての責任の所在を明確にすることが望ましいです。そのため、 賃貸不動産経営管理士が作成した場合は、記名(署名)することが推奨されます。
【本肢】
本肢は、「長期修繕計画書の作成が賃貸住宅の資産価値を維持する上で重要であること」「賃貸不動産経営管理士が作成した場合、責任の所在を明確にするために記名することが望ましい」と述べられており、これは適切な記述です。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険