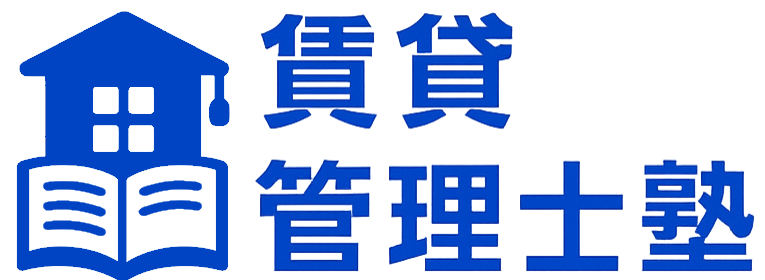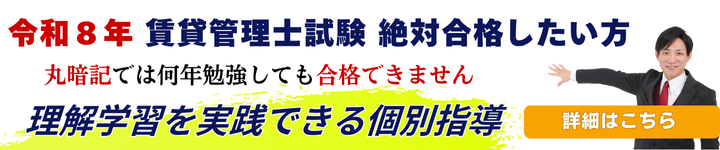賃貸住宅の維持保全に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 機器の交換は、劣化状況と収支状況に鑑み、法定耐用年数のみにとらわれず実施することが求められる。
- 事故や故障が起きてから修繕を行うのではなく、事故や故障が起きないようにあらかじめ適切な処置を施すことが必要である。
- 事故や故障の復旧を急ぐあまり、十分な検証をせずに部分的補修をすると設備全体の修繕周期の把握が困難となることが多い。
- 経済的な観点からは、事故や故障が起きてから修繕を行う事後保全が望ましい。
【答え:4】
1.機器の交換は、劣化状況と収支状況に鑑み、法定耐用年数のみにとらわれず実施することが求められる。
1・・・ 適切
機器には法定耐用年数が設定されています。しかし、法定耐用年数どおりに機器を交換することにとらわれることなく、現場の劣化状況と収支状況を考え合わせ、予防的に交換・保守・修繕することが管理業者には求められます。よって、本肢は適切です。
この点は 対比ポイントがあるので、個別指導で解説いたします!
2.事故や故障が起きてから修繕を行うのではなく、事故や故障が起きないようにあらかじめ適切な処置を施すことが必要である。
2・・・ 適切
賃貸住宅の維持保全は、問題が起きてから行うのではなく、問題が起きないよう、あらかじめ適切な処置を行う必要があります。これを「予防保全」と言います。予防保全には以下のようなメリットがあります。
- 修繕コストの削減
早めの対応により、大規模な修理が不要になり、長期的なコストを抑えられます。 - 入居者の満足度向上
設備のトラブルを未然に防ぐことで、快適な居住環境を維持できます。 - 建物の寿命を延ばす
定期的なメンテナンスにより、建物や設備の劣化を防ぎ、資産価値を維持できます。
3.事故や故障の復旧を急ぐあまり、十分な検証をせずに部分的補修をすると設備全体の修繕周期の把握が困難となることが多い。
3・・・ 適切
事故や故障は突然起き、事後保全でその復旧を急ぐあまり、十分な検討をせずに部分的な補修をしたり、性能や耐久性が異なる部品に交換することで、設備全体の修繕周期が把握できなくなることが多いです。よって、本肢は適切です。
この点も周辺知識も重要なので、個別指導で解説します。
4.経済的な観点からは、事故や故障が起きてから修繕を行う事後保全が望ましい。
4・・・ 不適切
経済的な観点からも、事故や故障が起きる前に適切な点検・補修を行う予防保全が望ましいです。よって、不適切です。
予防保全の場合、定期点検を行い、小さな不具合を早期に発見・修繕できるため、大規模な修理が不要になり、結果として、長期的に修繕コストを抑えられます。
令和6年・2024年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 建物賃貸借契約
- 問5
- 委任契約
- 問6
- 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針
- 問7
- 賃貸住宅管理業法
- 問8
- 賃貸住宅管理業法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 少額訴訟
- 問12
- 建物調査
- 問13
- 建築基準法
- 問14
- 建築基準法
- 問15
- 建物設備
- 問16
- 建物設備
- 問17
- 建物設備
- 問18
- 賃貸借
- 問19
- 賃貸住宅管理業法
- 問20
- 賃貸借
- 問21
- 賃貸借
- 問22
- 賃貸借
- 問23
- 賃貸借
- 問24
- 保証契約
- 問25
- 賃貸借
- 問26
- 賃貸住宅管理業法
- 問27
- 賃貸住宅管理業法
- 問28
- 賃貸住宅管理業法
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 特定転貸事業者
- 問33
- 特定転貸事業者
- 問34
- 特定転貸事業者
- 問35
- 特定転貸事業者
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 消費者契約法
- 問40
- 特定家庭用機器再商品化法
- 問41
- 賃貸住宅管理
- 問42
- 賃貸不動産経営管理士
- 問43
- 借主の募集
- 問44
- 税金
- 問45
- 証券化事業
- 問46
- 建物管理
- 問47
- 建物管理
- 問48
- 建物管理
- 問49
- 賃貸不動産経営管理士
- 問50
- 保険