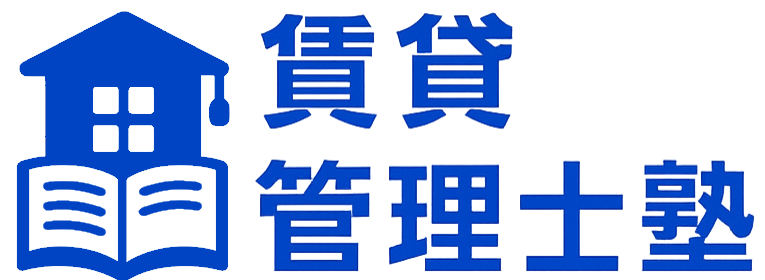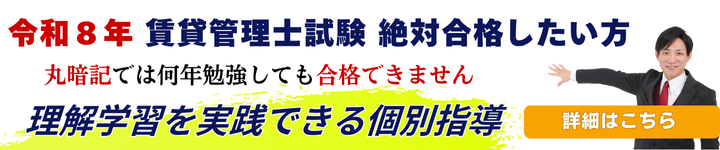- 建物は時間の経過とともに劣化するので、長期修繕計画を策定し、維持管理コストを試算することは有益である一方、その費用は不確定なことから賃貸経営の中に見込むことはできない。
- 長期修繕計画は、数年に一度は見直しを行うことにより、適切な実施時期を確定することが必要である。
- 長期修繕計画によって修繕費とその支払時期が明確になることから、将来に備えて計画的な資金の積立てが必要となる。
- 計画修繕を実施することで、住環境の性能が維持でき、入居率や家賃水準の確保につながり、賃貸不動産の安定的経営を実現できる。
1・・・不適切
建物は時間の経過とともに当然劣化します。そのため、長期修繕計画を策定し、維持管理コストを試算することは有益です。長期的な視野に立ち、いつ・どこをどのように・いくらぐらいで修繕するのかをまとめたものを、長期修繕計画といいます。計画した修譜を着実に実施していくためには、資金的な裏づけを得ることが必要であり、長期修繕計画を策定して維持管理コストを試算し、維持管理費用を賃貸経営のなかに見込まなければなりません。
本肢は「費用は不確定なことから賃貸経営の中に見込むことはできない」という記述が誤りです。
2・・・適切
計画修繕を実行する前に「長期修繕計画」を作成し、修繕のおおよその時期を把握し、日常的な清掃や点検によって、実際の修繕を効果的に実施するタイミングを判断します。2、3年に1度は修繕計画内容を見直すことで適切な修繕時期等を確定します。そして、修繕時期が近づいた場合には、専門家による劣化診断や精密な検査を行い、その結果に基づいて修繕内容を具体的にして、工事費用の見積りを徴収して大規模修繕工事等を実施します。
3・・・適切
長期修繕計画によって、長期間における修繕費とその支出時期が明確になることから、将来に備えて計画的な資金の積立てが欠かせません。また、毎年の修繕費用も年数を重ねると相当な金額となることから、修繕積立金の変更の必要性の有無については管理業者が早い段階で検討して入居者の理解に努めます。
4・・・適切
適切な計画修繕を実践することで、住環境の性能が維持でき、高い入居率や家賃水準の確保につながり、次の修繕のための資金入居者にも安心・満足して暮らせる住まいを将来にわたって提供できます。
令和3年・2021年の賃貸不動産経営管理士過去問
- 問1
- 賃貸住宅管理業法
- 問2
- 賃貸住宅管理業法
- 問3
- 賃貸住宅管理業法
- 問4
- 賃貸住宅管理業法
- 問5
- 賃貸住宅標準管理受託契約書
- 問6
- 賃貸住宅の管理
- 問7
- 賃貸住宅の管理
- 問8
- 民法
- 問9
- 原状回復ガイドライン
- 問10
- 原状回復ガイドライン
- 問11
- 防犯配慮設計指針
- 問12
- 建築基準法(単体規定)
- 問13
- 耐震改修
- 問14
- 修繕履歴情報
- 問15
- 建物の維持保全
- 問16
- 建物設備(屋上・外壁)
- 問17
- 建物の修繕
- 問18
- 建物設備(給水設備・給湯設備)
- 問19
- 建物設備(換気設備)
- 問20
- 賃貸借(敷金)
- 問21
- 賃貸借(賃料増減核請求)
- 問22
- 賃貸借(賃料回収・明渡し)
- 問23
- 賃貸借(賃貸住宅標準契約書)
- 問24
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問25
- 賃貸借(建物賃貸借)
- 問26
- 賃貸借(定期建物賃貸借)
- 問27
- 賃貸借・保証
- 問28
- 賃貸借(所有権の移転)
- 問29
- 賃貸住宅管理業法
- 問30
- 賃貸住宅管理業法
- 問31
- 賃貸住宅管理業法
- 問32
- 賃貸住宅管理業法
- 問33
- 特定賃貸借標準契約書
- 問34
- 特定賃貸借標準契約書
- 問35
- 特定賃貸借標準契約書
- 問36
- 特定転貸事業者
- 問37
- 特定転貸事業者
- 問38
- 特定転貸事業者
- 問39
- 特定転貸事業者
- 問40
- 特定転貸事業者
- 問41
- 特定転貸事業者
- 問42
- 賃貸住宅管理業法
- 問43
- 賃貸不動産経営管理士
- 問44
- 宅地建物取引業法
- 問45
- 税金
- 問46
- 賃貸住宅
- 問47
- 業務上の関連法令
- 問48
- 賃貸不動産経営管理士
- 問49
- 保険
- 問50
- 不動産賃貸経営