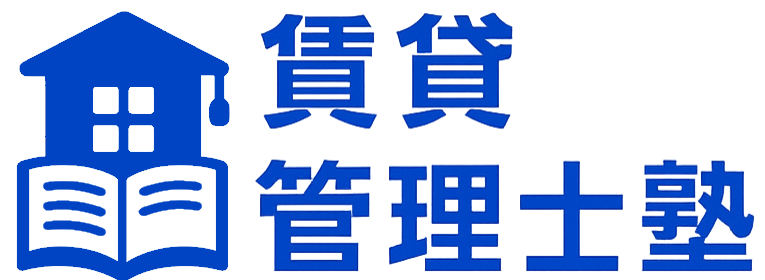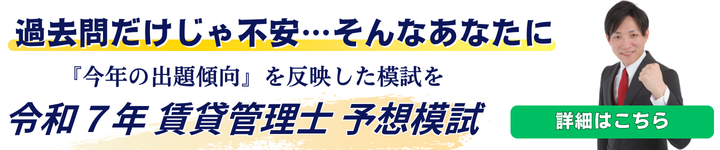賃貸借契約の成立

賃貸借は、賃貸人(貸主)が、賃借人(借主)に対して、「物の使用および収益」を約束し、賃借人が、賃貸人に対して、「賃料を支払うこと」及び「契約が終了したとき引き渡しをを受けた物を返還すること」を約束(合意)することですることで、成立します(民法601条)。つまり、意思表示の合意によって成立します。これを「諾成契約」と言います(民法522条1項)。
注意点
賃貸人の義務
使用収益させる義務
賃貸人は、賃借人に対して、 契約と目的物の性質により定まった使用方法 (用法) に従って、目的物を使用および収益させる義務を負います(民法601条)。分かりやすく言うと、例えば、居住用建物(住むための部屋)を賃貸する場合、賃貸人は、居住用建物を賃借人に引き渡す義務も負います(鍵を渡す義務を負う)。さらに、賃貸人は賃借人に対して、住むために支障となる障害を除去しなければなりません。例えば、貸した建物に別の人が住んでいたのであれば、その人にどいてもらう義務も負います。
修繕義務
賃貸人は、賃貸物の使用および収益に必要な修繕義務を負います(民法606条1項)。例えば、居住用建物を賃貸して、その建物の屋根が壊れていて雨漏りをしている場合、賃借人は、住むことができません。そのため賃貸人は、屋根を修理する義務を負います。
そして、修繕費用は、通常、賃料に含まれているので、賃借人は負担しません。賃貸人が修繕費用を負担します。これは、地震などの不可抗力により生じた修繕についても同様、賃貸人は修繕義務を負います(修繕費用は賃貸人負担)。
賃借人による修繕
賃借人が使用収益を行うために必要な修繕は、賃貸人が行わなければなりません。しかし、賃貸人が必要な修繕を行わない場合には、賃借人の使用収益に支障が生じます。例えば、居住用建物において、屋根が壊れて雨漏りがあった。これを賃貸人が直さない場合、賃借人は、住むことができません。そこで、賃借人は、賃借物の修繕が必要である場合、①賃貸人に修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときには、賃借人は自ら修繕をすることができます。また、②上記通知をしなくても、賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないときも同様、賃借人は自ら修繕をすることができます。さらに、③急迫の事情があるときにも上記通知をせずに、賃借人は自ら修繕をすることができます。(民法第607条の2)。「急迫の事情」とは、例えば、雨漏りがしている状況で、近日中に台風が来る天気予報だった場合です。
修繕義務違反の効果
損害賠償請求
雨漏りしているのにもかかわらず賃貸人が屋根の修理を行わず、賃借人の所有する物品に損害が生じるなど、賃貸人が修繕義務を果たさないことが原因で賃借人に損害が生じた場合、賃借人は賃貸人に対し通常生ずべき損害の賠償を請求することができます(民法415条前段、第416条1項)。例えば、漏水が原因で、カラオケ店舗が浸水した事案について、賃貸人が修繕しなかったことが原因(賃貸人の修繕義務の不履行が原因)で営業することができなくなった場合には、債務不履行を理由として、損害賠償請求ができると判断しています(最判平21.1.19)。
必要費償還請求権
必要費とは、賃借物を通常の用法に適する状態に戻すために必要な費用を言います。例えば、居住用建物について、排水管が壊れて水漏れが発生している場合、水漏れがない状態、つまり住める状態に戻すための費用(排水管の工事費用)が必要費です。この必要費は、修繕義務がある賃貸人が負担します。それにもかかわらず、賃借人が修繕を行った場合(例えば、工事業者に工事を頼んで修理代金を賃借人が負担した場合)、賃借人は賃貸人に対して費用の償還請求(返還請求)をすることができます(民法608条1項)これを「必要費償還請求権」と言います。
そして、この必要費は、賃貸人は直ちに賃貸人に支払う義務があります。それにも関わらず、賃貸人が賃借人に対して、必要費を払わない場合、賃借人は「必要費償還請求権」を被担保債権として(守るために)留置権を行使することができます(民法295条)。分かりやすく言うと、賃借人は賃貸人に対して「必要費を返してくれないなら、建物を返しません!」と主張でき、留置権に基づき目的物の明渡しを拒むことができます。ただし、留置権を行使したとしても、賃借人は、賃料は払わないといけません。
また、必要費(修繕義務)は、賃貸人と賃借人との間の合意で、賃借人負担にすることも可能です。
留置権とは
他人の物(建物)を占有している者(賃借人)が、 必要費の弁済を受けるまで、物(建物)を自分(賃借人)のところに「とどめておく権利」、これを留置権と言います。例えば、AがBに自動車の修理を出し、修理業者Bが修理完了したが、Aが代金を支払わない場合、Bは自動車に対して留置権を主張し、自動車の引き渡さず、とどめておくことがあげられます。
有益費償還請求権
有益費とは、賃借人が目的物(賃貸物)の改良のために支出した費用を言います。イメージとしては、価値を高めるための費用で、例えば、建物の賃貸において、建物に床暖房を設置するための費用です。
そして、「有益費償還請求権」とは、契約終了時に物件の価格の増加が現存する場合に、「①支出した費用」または「②増加額」を、賃借人が賃貸人に請求できる権利を言います。(民法196条2項、608条2項)。「①支出した費用」または「②増加額」については、賃貸人が選択するので、通常、安くなる「②増加額」が選択されるため、②増加額を請求する形になります。例えば、床暖房の設置費用として30万円かかったとします。その後、契約終了時には、10万円の価値まで下がった場合、①支出した費用は30万円、②増加額は10万円なので、賃借人は、賃貸人に対して10万円を請求することになります。
また、賃貸人と賃借人との間の合意により、有益費は賃借人負担とし、有益費償還請求権を認めない特約も有効です。
造作買取請求権
造作とは、賃借人が賃借物を利用しやすくするために、賃貸人の同意を得て、 建物に設置するもので、取り外しが可能な物を指します。例えば、畳やエアコン等です。
そして、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作を、契約終了の際に、賃貸人に対して時価で買取請求をすることができます。これを造作買取請求権と言います。 「時価」とは、通常、その時に売買した場合の金額です。
そして、この「造作買取請求権」は特約で排除することができます。つまり、賃貸人と賃借人との合意により、「造作買取請求はできませんよ!」 と約束してもOKということです。
造作買取請求権では建物を留置できない
造作は、上記の通り、取り外しができます。したがって、もし、賃貸人が造作買取請求をしてもお金を払ってくれない場合、造作(例えば、畳やエアコン)を賃借人が取り外して持っていけばいいだけです。そのため、造作の費用を賃貸人が払ってくれないからといって、建物自体を留置することは出きません。つまり、造作の費用を賃貸人が払ってくれなかったとしても、賃借人は、建物の明渡を拒むことは出きません。
賃料支払義務
賃借人は、賃貸人に対して賃料支払義務を負います。この賃料は目的物(建物)使用させてもらう対価です。もし、賃借人が、第三者に転貸していたとしても、賃借人は、賃貸人に対して、賃料を負担しなければなりません。
賃料の支払時期
賃料の支払時期は、特約がなければ当月分を当月末払いです(後払いが原則)。特約があれば特約に従います。現在は、前月末(あるいは、前月中の所定の日)とする前払いの特約とする場合が多いです。
賃料の支払場所
賃料の支払場所は、特約がなければ債権者(賃貸人)住所に持参します(持参払いが原則)。特約があれば特約に従います。現在は、多くの賃貸借契約において、銀行口座に振り込む方法が採られているので、その場合、支払場所は、銀行口座となります。
建物が全部滅失した場合・一部滅失した場合どうなるか?
賃貸人が建物を使用させることができなければ、賃借人に賃料支払義務は生じません。これは、地震や第三者による放火のような「天災や不可抗力」のように賃貸人の責任ではない事由によって、建物が使用できなくなった場合も同様、賃料は発生しません。
賃借人の責任ではなく、建物が全部滅失した場合
地震や第三者による放火のような「天災や不可抗力」によって、建物が全壊・全焼した場合、賃借人は、当然に賃料全額を支払う義務がなくなります。つまり、契約解除をしなかったとしても、賃料を払わなくてもよいです。
賃借人の責任ではなく、建物が一部滅失した場合
地震や第三者による放火のような「天災や不可抗力」によって、建物の一部損壊・一部焼失した場合、賃借人は、使用できなくなった部分の割合に応じて、当然に減額されます(民法611条1項)。例えば、一つの部屋だけ使えなくなった場合、その部分の賃料だけ支払いを拒絶できます。なかなか計算をするのは難しいですが、例えば、10万円の家賃で、2万円減額され、8万円だけ払えばいい、といった感じです。
賃料債権の消滅時効
賃料債権を行使せず(つまり、賃貸人が賃借人に賃料を請求せず)、下記期間が経過すると、時効により賃料債権は消滅します。 時効期間は、下記1、2の通りで、いずれか一方の期間を経過したときは、賃料債権は消滅し、その後、賃貸人は賃借人に対して、賃料を請求することができなくなります。
- 賃貸人が権利を行使することができること(賃料の支払い期限が到来したこと)を知った時から5年間行使しないとき
- 権利を行使することができる時(賃料の支払い期限が到来した時)から10年間行使しないとき
※通常、賃料の支払い期限は、契約で定めています。そのため、支払い期限が到来した時点で、賃貸人は支払い期限の到来を知ることになるので、「1は、支払い期限が到来から5年」となります。そのため、2よりも先に1が到来するので、支払い期限が到来から5年が経過することで、賃貸人は賃借人に対して、賃料を請求することができなくなります。
弁済充当
弁済充当とは、債務者がお金を弁済した場合において、その弁済では、債務の全部を消滅させるのに不足がある場合に、その弁済をどの債務の弁済に充てるかをいいます。 つまり、弁済をしても、元本、利息及び費用の全部を消滅させるに足りないときに、どれから消滅をさせていくかということです。 例えば、賃料100万円の店舗で、賃料を滞納していたので、1万円の利息(遅延損害金)が発生した場合において、合計101万円の債務が存在します。ここで、賃借人が100万円を払った場合、賃料と利息のどれから弁済するかということです。
民法では、下記順番で考えるとしています。
- 合意(特約)があれば、その合意(特約)に従う。
- 合意がなければ、費用⇒利息⇒元本の順に充当する。
つまり、合意がない場合、利息1万円を払い、残り99万円は、賃料に充てられます。結果として、1万円の賃料がまだ未払いとして残ります。
複数の債務が存在していた場合どうなるか
例えば、賃借人が、おなじ賃貸人から甲建物と乙建物の2つを借りており、「甲建物の賃料」「乙建物の賃料」を滞納していたとします。この場合、どのような順番で充当するか?
- 弁済者(賃借人)が弁済の時において、その弁済を充当すべき債務を指定したら、それに従う。
- 弁済者がこの指定をしなかったときは、弁済受領者(賃貸人)がその受領の時において、どこから充当するか決めることができる。ただし、弁済者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、弁済者に決定権がある。
賃貸人も賃借人も指定しない場合どうなるか
上記は、「弁済受領者(賃貸人)」又は「弁済者(賃借人)」のいずれかが、充当する順番を決めています。しかし、どちらも決めない場合(指定しない場合)があります。そのような場合どうなるのか。
- 「弁済期にあるもの」と「弁済期にないもの」があるときは弁済期にあるものを先に弁済充当する。
- 弁済者(賃借人)の利益が多いものから先に弁済充当する。
- 弁済者(賃借人)の利益が同様の場合、弁済期が先に来たもの、または、先に来る予定のものから先に弁済充当する
供託
供託とは、債務者(賃借人)が債権者(賃貸人)に対してお金を支払おうとしているにもかかわらず、下記事由のいずれかに該当する場合、法務局(国の機関、役所)にある供託所にお金を預けて、債権者にお金を支払ったことにする制度です(民法494条)。
- 債権者(賃貸人)がお金の受領を拒絶している場合(受領拒絶)
- 債権者がお金を受領することができない場合(受領不能)
例えば、賃貸人の所在が分からない、賃貸人が不在の場合 - 債務者(賃借人)の過失なく、債権者が分からない場合(債権者不確知)
例えば、賃貸人死亡により、相続が発生し、誰が相続したか分からない場合
供託の効果
- 供託すると、賃借人の賃料支払義務は消滅します。
- 供託すると、賃借人は、債務不履行責任 (遅延利息など)を免れます。
そして、供託が行われた場合には、債権者(賃貸人)はいつでも債務者の承諾なく、供託所から、供託されたお金を受け取ることができます。
修繕に関する賃借人の義務
通知義務
修繕が必要なとき、賃借人は、遅滞なく、賃貸人に通知をしなければなりません。これが「通知義務」です。賃貸人がすでに修繕の必要があることを知っている場合は、通知は不要です。
受忍義務
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人にはこれに協力する義務があります。これを「受忍義務」と言います。「一時的に建物の明渡しが必要な場合」や「必要な修繕の前提として保守点検のために立ち入りを認めることが必要な場合」もあります。もし、明渡を拒んだり、立入りの求めに応じなかった場合(つまり、受忍義務違反の場合)、賃貸人は、賃借人に対して契約解除を請求することも可能です。
賃借権の譲渡と転貸の禁止
①賃借人は、賃借権の譲渡、転貸を無断でしてはなりません。つまり、賃借人は賃貸人の承諾なく、賃借権の譲渡、転貸をしてはいけません。
「賃借権の譲渡」と「転貸」の違い
賃貸人A、従前の賃借人B、賃借権の譲受人又は転借人Cとします。
- 「賃借権の譲渡」:従前の賃借人Bは、賃貸借契約から離脱するので、「賃貸人A」と「賃借権の譲受人C」との二者の賃貸借契約になる。(AB間の賃貸借契約は消滅する)
- 「転貸」:従前の賃借人Bの地位は残るので、「賃貸人Aと賃借人B」の賃貸借契約と、「賃借人Bと転借人C」の転貸借契約の2つの契約からなります。
賃貸住宅標準契約書の内容
第8条1項 賃借人は、賃貸人の書面による承諾を得ることなく、 本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は 転貸してはならない。
注意点