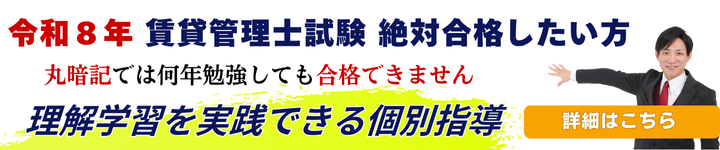支払時期
賃料は、原則として毎月末に支払わなければならず(民法614条)、後払いが原則です。ただし、当月分を前月末日までに支払う先払いとする特約は有効で、先払いの旨を賃貸人と賃借人との間で合意の上、賃貸借契約書に記載する必要があります。
支払場所
民法は、金銭債務の支払場所については、原則、債権者の住所に持参して支払う、としています(民法484条)。ただし、賃料の支払場所については、賃貸借契約において特約を定めることができ、特約によって銀行口座に振り込む方法としたり、口座振替の方法をとることも可能です。賃貸住宅標準契約書は、振込、口座振替、持参のうちから選択する方式をとっています(4条1項、頭書(3))。
振込手数料の負担
銀行口座に振り込む方法により賃料を支払う場合には、振込手数料をどちらが負担するかが問題となります。この点について、民法には、弁済の費用について別段の意思表示がないとき(特約がないとき)、その費用は、債務者が負担すると定められており(民法485条本文)、振込手数料は、特約がなければ賃借人負担となります。特約があれば、特約に従います。
賃料債権の消滅時効
賃料債権は、時効により消滅します。ただし、時効期間の経過により当然に消滅するわけではなく、消滅時効を援用する旨の意思表示が必要です(民法145条。大判大8.7.4)。これは民法通りの内容で、時効完成(時効期間満了)+援用によって、賃料債権は消滅し、援用後、賃貸人は、賃借人に対して、賃料を請求することができなくなります。
そして、賃料債権の時効期間には、下記2つがあります(民法166条1項)。下記、いずれか一方でも経過し、援用されると、賃料債権は時効により消滅します。
- 「権利を行使することができることを知った時」から5年
- 「権利を行使することができる時」から10年
賃料債権の場合は、賃貸人は、通常、「権利を行使することができる時」を知っています。つまり、賃料の支払い日を知っています。したがって、「権利を行使することができる時」=「権利を行使することができることを知った時」=「賃料の支払い日」となります。つまり、「賃料の支払い日から5年」が賃料債権の時効期間となります。
賃料改定特約
賃料は、賃貸人と賃借人の合意によって決められます。賃貸借契約を締結するときに決めることは当然ですが、一定期間経過後に賃料を改定することも可能です。そして、「一定の基準に従って当然に賃料を改定する旨の特約」もあります。例えば、「賃料を2年ごとに3%増額する」「固定資産税(あるいは土地路線価、物価指数など)の変動率にスライドして賃料を増減する」というような特約です。これを自動改定特約(スライド条項)と言います。自動改定特約は、あらかじめ賃料に関する紛争を回避する目的をもつものとして、内容が合理的であれば、有効です。
賃料増減請求
建物の賃料が、下記理由により不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増額または減額を請求することができます(借地借家法32条1項本文)。
- 土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増加・又は減少した
- 経済事情の変動により、土地又は建物の価格の上昇もしくは低下した
- 近傍同種の建物の借賃が増加した又は減少した
賃貸人からは増額請求ができ、賃借人からは減額請求ができます。この増額請求と減額請求をあわせて「賃料増減請求」と言います。
法律上、賃料増減額請求をすることができる要因として、上記1~3までが列挙されていますが、それ以外でも、事情を考慮し、総合的に不相当となったかどうかの判断がなされます。また、賃料改定は協議により行うとする条項が定められていても、賃料增減請求は可能です(最判昭56.4.20)。
そして、賃料増減請求権が行使されると、賃料は、請求が到達したときに、相当賃料の額にまで、増額または減額されます。これは、一方的な意思表示によって効力が生じるので、注意しましょう。
賃料増減請求の手続き
賃料増減請求権は、一般的には書面による通知によって権利を行使しますが、法律上、口頭でも有効としてます。
そして、「賃貸人が複数」いる場合、賃料増額請求権は、共有物の利用等の管理行為に当たるとされており(東京高判平28.10.19)、共有者の持分の価格に従い、その過半数で権利を行使しなければなりません(民法252条本文)。
調停前置主義
上記の通り、賃料増減請求権が行使されると、賃料は、請求が到達したときに、相当賃料の額にまで、増額または減額されます。これは、一方的な意思表示によって効力が生じます。しかし、請求を受けた側としては、納得がいかない場合があります。その場合、いきなり、裁判で訴えることはできず、事前に、調停の申立てをしなければなりません(調停前置主義。民事調停法24条の2)。
裁判所の判決が出るまでの賃料の取扱い
賃料増額請求について当事者間に協議が調わないときは、賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の賃料を支払えばよいです(借地借家法32条2項本文)。ただし、その裁判が確定した場合において、すでに支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければなりません(同項ただし書き)。
裁判が確定した場合において、すでに支払った額が過払いとなるときは、賃貸人は賃借人に過払額を返還しなければなりません。その場合、支払時から返還時までの過払額に付される利息は、年1割ではなく、「法定利率(3%)」となります。
賃料減額請求について当事者間に協議が調わないときは、賃貸人は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払いを請求することができます(同法32条3項本文)。ただし、その裁判が確定した場合において、すでに支払いを受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付けてこれを返還しなければなりません(同項ただし書き)。
裁判が確定した場合において、賃貸人の請求によって賃借人が支払った額が相当な額に不足するときは、賃貸人は賃借人に不足額を追加で請求することができます。この場合、返還時までの不足額に付ける利息は、「法定利率(3%)」となります。
不増減特約
普通建物賃貸借では、一定の期間賃料を増額しない旨の特約(不増額特約)は有効です(借地借家法32条1項ただし書き)。一方、一定の期間賃料を減額しない旨の特約(不減額特約)については、その効力は認められません(無効)。つまり、不減額特約が定められていても、賃借人は賃料減額請求をすることができる。
定期建物賃貸借では、不増額特約と不減額特約のいずれも有効であって、特約の効力が認められます(同法38条7項)。定期建物賃貸借において、一定の期間賃料を増額または減額しない旨の特約を定めた場合には、増額と減額のいずれについても有効であり、賃貸人も賃借人も、定められた期間は賃料増額請求・賃料減額請求をすることはできなくなります。
問12-2:賃料の減額請求できない旨の特約と増額請求できない旨の特約は有効なのか無効なのか。.jpg)
賃料の回収業務が違法になる場合
未払賃料(未収賃料)を回収するために下記行為を行うと、違法となります。
- 鍵の交換やドアの鍵部分にカバーをかけるなどの方法によって賃借人が室内に立ち入ることができない状態にして、賃料の支払いを促すこと
- 室内から衣類、寝具、家具、器具その他の物品を持ち出すこと
- 勤務先など、賃借人の居宅等以外の場所に電話、訪問等をして督促すること(賃借人から連絡先を居宅等以外に指定されている場合は除外)
- 督促のために賃借人の居宅等を訪問した場合、賃借人からその場所から退去するよう要請されたにもかかわらず退去しないこと
- 賃貸人が、賃借人の勤務する会社の社長を通じて、明渡しを促すよう要求すること(社長から言ってもらうよう頼むこと)(横浜地判平2.5.29)
違法行為がなされると、刑事責任(住居侵入罪、器物損壊罪,建造物損壊罪など)を問われ、民事上の損害賠償義務(債務不履行、不法行為責任)を負います。また、管理業者の違法行為について、賃貸人の責任となる場合もあります(姫路簡判平21.12.22)。
(参考知識) 賃貸借契約書に、「賃借人が賃借料の支払いを怠ったときは、賃貸物件内にある動産を処分しても、異議の申立てをしない」などの特約を設けても、無効となります。
弁護士法との関係
弁護士でない者(非弁護士)は、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件および審査請求、異議申立て、再審査請求など行政庁に対する不服申立事件、その他一般の法律事件に関して、鑑定、代理、仲数、もしくは和解、その他の法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をすることを業とすることができない、と定められています。そのため、当事者本人以外の者が、法律事務とされる業務については報酬を得て行うことはできません。
そして、下記行為は、非弁行為となり違法となります。
- 管理を受託した管理業者が法律事務とされる業務を賃貸人の代理人として行うこと(例えば、訴訟の原告代理人となること)
- 未収賃料の回収について、管理業者が、その名において内容証明郵便を発信したり、訴訟を提起したりする行為
注意点
内容証明郵便
内容証明郵便は、「いつ」、「どのような内容」の郵便物を、誰が誰に宛てて差し出したかを郵便局(日本郵便株式会社)が証明する制度です(郵便法48条)。実際、送る書面を郵便局が写真を撮って保管してくれます。あくまで、内容証明郵便は、発送したことを証明してくれるだけで、到達したかは証明してくれません。そのため、到達も証明してもらうために配達証明付きの内容証明郵便を用いる場合が多いです。
公正証書
公正証書とは、公証人(司法試験に合格した人)が作成する文書です(公証人法1条1号)。公正証書は公文書であって、法律上社会的に信頼できる文書として取り扱われています。そして、公正証書の原本は、原則として、20年間、公証役場で保管されます(公証人法施行規則第27条)。
公正証書の執行力
そして、公正証書は、一定金額の金銭支払いなどを目的とする請求に関する文書であり、債務者の同意を得て、債務者が直ちに強制執行に従う旨の陳述が記載されている場合、公正証書により強制執行をすることができます(民事執行法22条5号)。
裁判をしなくても直ちに強制執行をすることが可能であるため、債務者に対し心理的な圧迫を与え、任意の履行を促す効果も大きいです。
そのため、金銭支払いについて執行力のある文書を作成するために公正証書が利用されることが多いです。
注意点
支払督促
裁判所の手続きにより、未収賃料を回収する方法があります。その一つとして「支払督促(しはらいとくそく)」があります。賃貸人が、簡易裁判所の書記官に対して、支払督促の申し立てをし、簡易裁判所の書記官は、実質的な審査をせずに、支払督促(支払命令)を出すものです(民事訴訟法382条)。支払督促に対し、異議のある賃借人(債務者)は、異議の申し立てができ、異議が申し立てられると、訴訟手続に移行します。つまり、異議申し立てをすることで、賃借人(債務者)は厳格な審理を求めることができます。もし、債務者が異議申立てをせず、なおかつ支払いがない場合には、債権者は「仮執行宣言の申立て」を行うことができます。
仮執行宣言
仮執行宣言とは、裁判が確定する前でも執行することのできる効力を与えるものです。判決で「被告(賃借人)は原告(賃貸人に)に金〇〇円を支払え」と言い渡されると、賃貸人(債権者)は、強制執行を使って、預金などを差し押さえて、強制的に回収することができます。これを執行力といいます。この執行力は、判決が確定して、はじめて生じるのが本来ですが、手続きが遅くなると、財産が散逸してしまったり、所在不明になったりすることがあります。また、賃借人がわざと上訴して執行を引き延ばすという悪用の可能性もあります。それでは、せっかく勝訴しても意味がなく、民事訴訟制度の意義が失われてしまいます。そこで、支払督促に、裁判所書記官が仮執行宣言を付けなければなりません(民事訴訟法391条)。
少額訴訟
少額訴訟とは、簡易裁判所が管轄する少額の訴訟で、複雑困難でないものについて、一般市民が訴額に見合った経済的負担で、迅速かつ効果的な解決を求めることができるように、原則として1回の期日で審理を完了して、直ちに判決を言い渡す訴訟手続である(民事訴訟法368条1項)。
- 請求金額は60万円以下
- 審理は1回のみで、反訴はできない
- 1回目の期日で直ちに判決がなされる
- 控訴はできない
- 同一の簡易裁判所において、同一の年に10回を超えて少額訴訟を提訴できない